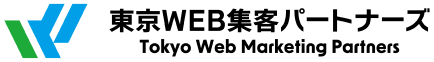Webマーケティング研究会の小林です。
業界関係者の集まる会でセミナー講師や社内の勉強会などで「話してください」というのはときどきあることで、そうした機会が新たな顧客獲得や思いがけない人とのつながりを生むことは少なくありません。
他人にわかりやすく自分が知っていることを説明するのは意外に難しいもので、開催までの時間がそれほどない場合、まず募集をかけてからその内容を開催直前まで考えようと、募集時にはタイトルと講師略歴だけの告知をされる方もいらっしゃると思います。
一方で申込する側からすると、タイトルだけで内容の目次すらないセミナーには期待する話が聞けるか、自分が参加して場違いではないか迷うところがあると思います。
そこでおススメしたいのが生成AIの活用です。
やってみました
財務3表モデリングの作成法を説明する機会がありました。
その際には生成AIを使わずに構成を考えたのですが、同じようなお題で生成AIに構成案作成を依頼したところ自分で作ったものとかなり近い同じものが作成されたのでご紹介したいと思います。
最初から生成AIに構成案作成を依頼すれば、イベント告知時点で目次を入れた案内を出すことが容易になります。
生成AI(Chat GPT)が作成した案のうち、私が構成に入れてなかった部分、つまりありがたい追記を緑字にします。逆に私の構成にあってChatGPTの構成になかったもの、つまり私的には物足りなかったので追記した点を青字で追記します。
プロンプト(例)
♯背景
あなたは企業会計の専門家です。私は簿記を習ったことがない人に、財務3表モデリングができるようになる勉強会を開催したいと考えています。2時間×3-4回で白紙のエクセルからカフェなどのシンプルな事業の3表モデルができるようになる内容を考えています。
♯指示
勉強会の目次、各回の内容を提案してください。
♯備考
足りない情報はあなたが私に質問してください。
生成AIによるセミナー構成案(の例)
各回の概要
第1回:財務諸表の基本とエクセルモデリングの準備
1. オリエンテーション・学習ゴールの共有
2. 財務3表の基礎知識
3. カフェ事業のビジネスモデル概観(設立時想定事項と運営期想定事項)
4. エクセルモデリングの準備 モデリング用エクセル操作基礎演習(カーソル移動、必須ショートカット15)
5. 簡単な演習
第2回:損益計算書(P/L)の作成と貸借対照表(B/S)の基礎
1. 前回の復習と質疑応答 (ちょっと関数と数式が複雑な)固定資産・減価償却と長期借入・返済想定表の作成
2. P/Lモデルの詳細設計(PLツリーの作成)
3. 貸借対照表(B/S)の基礎
4. エクセル演習:P/L作成からB/Sへの反映
第3回:貸借対照表(B/S)の完成とキャッシュ・フロー計算書(C/F)の作成
1. 前回までの復習と質疑応答
2. B/Sの詳細構築
3. キャッシュ・フロー計算書(C/F)の基本
4. エクセル演習:C/Fシートの作成と3表の連動チェック(B/Sがバランスしないときの注目点)
第4回(オプション):モデルの応用とシミュレーション ※全3回でも一通りモデルは完成しますが、より実践的な分析・応用を学ぶための追加回です。
1. 財務3表の完成版確認
2. シナリオ分析・感度分析
3. 経営指標・分析手法の紹介
4. 質疑応答・今後の学習ロードマップ (希望者のみ)自身の考える事業の3表作成演習
質問例(不足情報の確認)
1. 対象参加者の人数・レベル感は? Excel操作にどれくらい慣れているか、会計用語に対する理解度をどの程度想定しているか 民間企業にいたことがあるか
2. 希望するモデルの細かさや期間は? 月次ベースか年次ベースか、どこまでリアルなシミュレーションを行うか(在庫回転や借入金金利など)
3. モデリングの演習で使う具体的な事例は? カフェを想定するが、他のサービス業や小売業の例も含めるか 受講者がイメージしやすい事例の要望があるか
4. ゴール後の活用イメージは? 自分のビジネスアイデアを数字で形にする コンサル・投資家向けのプレゼン資料に使う 仕事での予算管理、計数管理に活かす
最後に
以上のように7割前後の項目は自分で考えたものと同様のものを出してくれました。
(実際には各項目1-3行の内容も入っていましたが長くなるので省略しました。)
もちろん、AIの出力はそのまま使わずご自身で内容の正確さの確認や不適切な表現がないかを確認することが必要です。
その上でここからご自身の経験に基づいて理解されやすい順番に変えたり、受講者の知識・スキルに応じて説明内容を加減したりするのであればそれほど時間がかからないかと思います。
それに加えて、受講者について確認しておくことの整理や、他人にわかりやすく伝えるために、自身も知識を補ったり習熟しておくべき項目が示され、準備すべき項目が明確になりました。
こうした構成案の要約をイベント告知時にお伝えすることでターゲット層の人がより応募しやすくなると思います。
セミナー講師、勉強会の演者を頼まれた際には、ご活用を検討されてはいかがでしょうか。